企業について
マルチプル関連
| 日付 | 2025/6/16 | |||
| 時価総額(億円) | 2,591億円 | |||
| 株価(円) | 3,376.0円 | |||
| PER | 11.0倍 | |||
| PBR | 0.84倍 | |||
| 利回り | 4.03% | |||
| ROE(予) | 7.65 | 2026.03予想 | ||
| 信用倍率 | 93.11倍 | |||
| ネットキャッシュ | 1685億 | ※流動資産+投資有価証券×0.7-負債 | ||
| ネットキャッシュ比率 | 0.65 | ※ネットキャッシュ/時価総額 | ||
| キャッシュニートラルPER | 3.85 | ※PER×(1-ネットキャッシュ比率) | ||
| 取引のサイト(L or S) | L | |||
| 目標株価 | 5219円 | ※PER×EPSで計算 17×307 | ||
|
株価の想定レンジ |
下はPER10倍程度 | ※ヒストリカルPERでレンジを予測 | ||
| レーティング |
2025/05/30
|
UBS 3600 東海東京 3400 |
||
ポジションの理由
2026年3月期の業績予想が弱く1000円近く叩き売られたところを購入した。
ツムラは日本の漢方市場で圧倒的なシェアを持つことから、費用の増加は価格転嫁できると思う。
(4)今後の見通し
2026年3月期の業績予想につきましては、売上高は主に国内医療用漢方製剤の販売数量増加に加え、中国事業の伸長により188,000百万円を見込んでおります。このうち中国事業の売上高は20,100百万円の見込みです。利益につきましては、主に償却費負担の大きい中国生産拠点における製造加工費の増加や生薬費の増加、人件費の増加などの影響で営業利益34,200百万円(14.8%減)、経常利益34,000百万円(19.9%減)、親会社株主に帰属する当期純利益23,000百万円(29.1%減)を見込んでおります。
2025年度の売上高は前年比20.1%増。大建中湯、抑肝散、牛車腎気丸の売上高は、不採算品再算定の適用を受け薬価が上昇した影響もあり、大きく増加した。これら漢方薬は医療機関で安定的に処方される薬剤であるため、コストに合わせた価格改定ができれば安定した売上高となる。
ネットキャッシュPER、利回り、ヒストリカルPERから現在の時価総額は割安水準。長期で持てば負けることはほぼないだろう。
以下、ツムラの競争優位性について
✅ ツムラの競争優位性
1. 処方範囲の網羅性(ラインナップ)
-
厚労省承認済みの医療用漢方製剤148処方のうち、129処方を取り扱い。
-
医師の「漢方ファーストチョイス」として確立されている。
2. GMP準拠の製造体制・品質管理
-
静岡工場・茨城工場などで、近代的設備と厳格なGMP対応を実施。
-
成分のばらつきが課題となる生薬に対し、独自の品質均一化技術を確立(例:抽出工程の標準化・HPLC分析)。
3. 原料の生薬調達力とサプライチェーン
-
中国などからの長期契約・自社農場との提携により安定供給を実現。
-
国内外の生薬栽培プロジェクトに投資し、**「原料の安全保障」**という観点で競合より先行。
4. 医療現場での信頼と実績
-
長年の学術活動、医師向け情報提供(MR活動)、エビデンス蓄積(RCT、リアルワールドデータ)により、医師の信頼を獲得。
-
全国の大学病院・診療所で標準治療として導入されている。
5. 研究開発とエビデンス創出
-
慶應義塾大学・東京大学などと連携し、漢方薬の科学的有効性を検証。
-
「統合医療」への接点強化にも注力(認知症、がん補助療法、更年期障害など)。
6. 法制度と保険適用の優位
-
医療用漢方薬は医療保険の対象。ツムラ製品はほぼすべてが保険収載されており、価格競争になりにくい。
- 一般用漢方薬(OTC)とは異なる参入障壁が高い領域。
-
⚠ 競合リスクや課題
項目 内容 競合 クラシエ、コタロー(小太郎漢方)、ジェネリック漢方(中堅製薬) 課題 原料生薬の価格高騰・気候リスク、漢方薬のエビデンス強化の継続的要求 将来戦略 海外展開(中国・東南アジア)や、認知症・がん領域での共同研究強化
🧠 まとめ
ツムラの競争優位性は、単なる製品の多さではなく、
**「信頼性 × 安定供給 × 科学的裏付け」**という3本柱に支えられています。
漢方薬が保険診療に含まれる日本独特の医療制度の中で、
ツムラは「ほぼ独占的地位」に近いポジションを確保しており、
中長期的にも安定性の高い企業といえます。
ツムラの「大建中湯(Daikenchuto, TU‑100)」に関する臨床試験について、国内外で蓄積されたエビデンスを整理しました。以下ご参考ください👇
🇺🇸 アメリカでの臨床開発
-
IND取得・第Ⅱ相治験進行中
-
2005年、FDAにINDを申請(2剤目)し、ミネソタ大学などで「術後イレウス」を対象とした治験を実施tsumura.co.jp+15tsumura.co.jp+15jstage.jst.go.jp+15。
-
現在、米国を中心にTU‑100を術後腸管機能回復支援として臨床開発中。第Ⅱ相試験が進行中と公式に発表されていますtsumura.co.jp+1yakuji.co.jp+1。
-
-
Mayo Clinic でのRCT(機能性便秘)
-
女性50名程度を対象に2.5gまたは5g ×3回/日を28日投与。腸管通過時間・腸機能・QOLへの顕著な改善効果は得られず、最小感覚閾値の低下が認められましたが、便頻度等には有意差なしでしたtrial.medpath.com+14yakuji.co.jp+14mhlw.go.jp+14。
-
🇯🇵 日本国内の臨床試験事例
-
術後イレウスへの適応検証
-
2009年前後より複数の多施設ランダム化二重盲検試験が行われ、大腸がん・肝切除後などで、初回排ガスの早期化、イレウス発症率低下、入院期間短縮などが示されていますjstage.jst.go.jp。
-
-
へパテクトミー(肝切除)後の試験(UMIN登録)
-
UMIN000002952/R000003589に登録。ヘパテクトミー患者約20名を対象に、腹部膨満およびQOLを14日間評価。結果の詳細は未公開ですが「探索的有効性・安全性評価」を目的としたインターベンション試験ですtsumura-usa.com+15upload.umin.ac.jp+15upload.umin.ac.jp+15。
-
-
便秘・腹部膨満に対する試験
-
2013年開始、20名規模。慢性便秘に伴う腹部膨満感への有効性を探る試験(UMIN000008070)rctportal.niph.go.jp。
-
-
便失禁患者への探索的研究
-
UMIN000030252(2017登録)により、便失禁患者の腹痛・腹部膨満への効果と安全性を評価upload.umin.ac.jp。
-
🧪 基礎・機序研究
-
ラット結腸モデル
-
DKTは腸管内でpropagating contractionを誘導し、コロン輸送時間を有意に短縮。成分のhydroxy‑α‑sanshoolがenteric nervous systemを活性化する機序が示唆されましたtsumura.co.jp+2pmc.ncbi.nlm.nih.gov+2jstage.jst.go.jp+2。
-
-
抗炎症と腸内免疫への作用
-
RIKENによる研究では、大建中湯が腸内細菌叢を調整し、Group 3 ILCを増やすことで、実験的腸炎を軽減する作用が報告されていますrctportal.niph.go.jp+9riken.jp+9jstage.jst.go.jp+9。
-
✅ 総まとめ
| 領域 | 試験対象・形態 | 主な評価結果 |
|---|---|---|
| 米国(Mayo Clinic) | 機能性便秘(女性)28日投与、RCT | 感覚閾値に差異、全体として明確な改善なし |
| 米国開発 | 術後イレウス/ERAS併用(第Ⅱ相進行中) | 安全性・有効性確認中 |
| 日本国内 | 肝切除後/術後大腸手術後/便秘/便失禁など | 排ガス早期化、腹部膨満改善など有望結果 |
| 基礎研究 | ラットモデル/免疫調節作用 | 腸管運動促進・免疫改善のメカニズム解明 |
🔍 今後の展望・注目点
-
アメリカ第Ⅱ相治験の成否が、FDA承認への鍵。
-
多施設共同第Ⅲ相試験へ進む予定(国内外問わず)。
-
機能性便秘など非手術後疾患への適応拡大を目指す臨床試験も継続中。
考えられるリスク

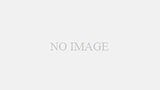
コメント